だんだん秋が深まってきて、暖かい服装、温かい料理に惹かれるようになってきましたね。今週もベイシアから旬のおいしい話題をお届けします。
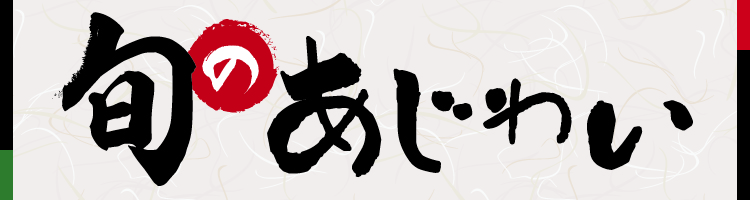
これからの季節にぴったりの温かい料理といえば、鍋料理。そして、鍋料理に欠かせない野菜のひとつが大根です。

スライスして鍋に入れたり、大根おろしにして薬味にしたり、みぞれ鍋にしたり。冬の食材として身近な野菜である大根は、昔から日本人に親しまれてきました。
そのため、大根にまつわることわざや慣用句がいろいろあります。そこにはどんな意味が込められているのか、見ていきましょう。
「大根どきの医者いらず」大根の収穫時期には、みんなが健康になり医者がいらなくなるという意味。大根は消化を助けることで、昔から体に良いとされてきました。
「大根頭にごぼう尻」大根は頭の方が、ごぼうは下の方がおいしいという意味。大根は先の方が辛く、頭の方が甘く感じられます。ごぼうはその逆で、先の方が柔らかくておいしいとされています。
「大根食ったら菜っぱ干せ」大根の葉のようにいつもは捨ててしまうものも、役に立つ場合があるという意味。大根の葉には栄養分が豊富に含まれているので、活用したいものですね。
「大根役者」大根でお腹をこわすこと、あたることは滅多にありません。このことから、「あたらない」つまりウケない役者を意味するようになりました。
「大根を正宗で切る」名刀で知られる正宗で大根を切る、つまり必要以上に大げさな行動をすること。あるいは道具や才能の使い方が適していないこと。名刀には名刀の使い道があり、大根もおいしく食べることで活かされると言えますね。
いかがですか? ことわざや慣用句を見ると、大根に関する暮らしの知恵や、大根の特性などがわかってきます。覚えておくと、いつか役に立つ機会があるかもしれません。
参考:
「農産物の故事・ことわざ」農林水産省
「会話で使えることわざ辞典」imidas
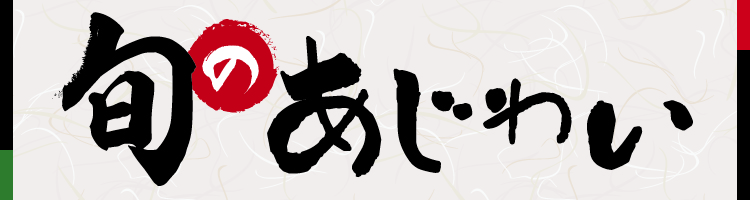 これからの季節にぴったりの温かい料理といえば、鍋料理。そして、鍋料理に欠かせない野菜のひとつが大根です。
これからの季節にぴったりの温かい料理といえば、鍋料理。そして、鍋料理に欠かせない野菜のひとつが大根です。
 スライスして鍋に入れたり、大根おろしにして薬味にしたり、みぞれ鍋にしたり。冬の食材として身近な野菜である大根は、昔から日本人に親しまれてきました。
そのため、大根にまつわることわざや慣用句がいろいろあります。そこにはどんな意味が込められているのか、見ていきましょう。
「大根どきの医者いらず」大根の収穫時期には、みんなが健康になり医者がいらなくなるという意味。大根は消化を助けることで、昔から体に良いとされてきました。
「大根頭にごぼう尻」大根は頭の方が、ごぼうは下の方がおいしいという意味。大根は先の方が辛く、頭の方が甘く感じられます。ごぼうはその逆で、先の方が柔らかくておいしいとされています。
「大根食ったら菜っぱ干せ」大根の葉のようにいつもは捨ててしまうものも、役に立つ場合があるという意味。大根の葉には栄養分が豊富に含まれているので、活用したいものですね。
「大根役者」大根でお腹をこわすこと、あたることは滅多にありません。このことから、「あたらない」つまりウケない役者を意味するようになりました。
「大根を正宗で切る」名刀で知られる正宗で大根を切る、つまり必要以上に大げさな行動をすること。あるいは道具や才能の使い方が適していないこと。名刀には名刀の使い道があり、大根もおいしく食べることで活かされると言えますね。
いかがですか? ことわざや慣用句を見ると、大根に関する暮らしの知恵や、大根の特性などがわかってきます。覚えておくと、いつか役に立つ機会があるかもしれません。
参考:
「農産物の故事・ことわざ」農林水産省
「会話で使えることわざ辞典」imidas
スライスして鍋に入れたり、大根おろしにして薬味にしたり、みぞれ鍋にしたり。冬の食材として身近な野菜である大根は、昔から日本人に親しまれてきました。
そのため、大根にまつわることわざや慣用句がいろいろあります。そこにはどんな意味が込められているのか、見ていきましょう。
「大根どきの医者いらず」大根の収穫時期には、みんなが健康になり医者がいらなくなるという意味。大根は消化を助けることで、昔から体に良いとされてきました。
「大根頭にごぼう尻」大根は頭の方が、ごぼうは下の方がおいしいという意味。大根は先の方が辛く、頭の方が甘く感じられます。ごぼうはその逆で、先の方が柔らかくておいしいとされています。
「大根食ったら菜っぱ干せ」大根の葉のようにいつもは捨ててしまうものも、役に立つ場合があるという意味。大根の葉には栄養分が豊富に含まれているので、活用したいものですね。
「大根役者」大根でお腹をこわすこと、あたることは滅多にありません。このことから、「あたらない」つまりウケない役者を意味するようになりました。
「大根を正宗で切る」名刀で知られる正宗で大根を切る、つまり必要以上に大げさな行動をすること。あるいは道具や才能の使い方が適していないこと。名刀には名刀の使い道があり、大根もおいしく食べることで活かされると言えますね。
いかがですか? ことわざや慣用句を見ると、大根に関する暮らしの知恵や、大根の特性などがわかってきます。覚えておくと、いつか役に立つ機会があるかもしれません。
参考:
「農産物の故事・ことわざ」農林水産省
「会話で使えることわざ辞典」imidas